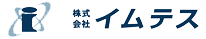- 水質検査について
-
- 浴槽水(レジオネラ)について
-
- Q新聞などで見かけるレジオネラってなに?
- A
レジオネラは、土壌や河川など自然環境に広く生息している細菌です。ぬるい水を好み、アメーバなどの原生動物に寄生して増殖します。
ちなみに「レジオネラ」という名前は、1976年にアメリカの在郷軍人会総会(the Legion)で集団発生したことにより発見されたことが由来となっています。
- Qレジオネラ症ってどんな病気?
- A
レジオネラ症は主に肺炎として現れます。特に高齢者や糖尿病患者など抵抗力の弱い人で発症しやすく、また他の細菌性肺炎との区別がつきにくいため、早期治療を行わなかった場合の致死率は非常に高くなります。
- Qレジオネラ菌の主な感染経路は?
- A
レジオネラ属菌は、土壌や淡水から土埃とともに運ばれて、人工の池や滝、噴水、循環式浴槽、プール、加湿器などに入ります。水が停滞するような温かい場所ではぬめり(生物膜)が形成され、そこに繁殖したアメーバなどにレジオネラ属菌が寄生し、増殖します。最後にエアロゾル(小さな水しぶき)などを介して、レジオネラ属菌を人が吸い込むことで感染します。
- Qどんな水に検査が必要なの?
- A
代表的なものとして、浴槽水、冷却塔(クーリングタワー)、プール、噴水や人工池、ミスト噴霧装置、加湿器などが挙げられます。人が直接水に接触する施設や、エアロゾルが発生する設備があれば、検査を受けることをお勧めします。
- Q一般家庭でも感染のリスクがあるの?
- A
水道水を使う限りリスクは高くありません。
ただし、循環浴槽(いわゆる24時間風呂)や超音波式の加湿器などはリスクが高いので、配管や機器内部の定期的な清掃が必要です。
- Q循環式浴槽でのレジオネラ症防止対策はどんなものがあるの?
- A
- 浴槽水の塩素濃度などの測定を1日に1回以上実施します。(入浴者数やその他の要因により回数は増やします。)
- 浴槽水は1週間に1回以上の完全換水を行い、清掃と殺菌・消毒を行います。
- 浴槽水の検査は毎日換水している施設では、1年に1回以上、その他は1年に2回以上のレジオネラ属菌検査とその他の検査を実施します。
- 貯水タンクの温度は、60゜C以上に保持します。
- 集毛器(ヘアーキャッチャー)は、毎日清掃します。
- 消毒装置はチューブのエアかみや薬液による固化などの吐出不能の確認を実施します。
- ろ過器は逆洗浄を行い、必要に応じて薬品を使った高濃度殺菌洗浄を実施します。
- Qお風呂以外の水はどうやって管理したらいいの?
- A
プールや人が入ることを想定した人工池も、浴槽と同様の衛生管理を行うことが求められます。
また、業務用の加湿器やミスト噴霧装置は、水道直結にすることが望ましいです。貯水タンクを使う場合は、毎日の残留塩素濃度測定と定期的な洗浄・消毒を行いましょう。
いずれの設備においても、季節営業などの休止期間がある場合は、タンクや配管内で菌が増殖している可能性があるので、運転前清掃と検査を行うと良いでしょう。
- Qお風呂の水を飲んじゃった…
- A
もし浴槽水にレジオネラがいても、水を飲むだけでは感染しません。ただし、溺れてしまった場合は、水と一緒にレジオネラが肺に入った可能性があるので、発熱や呼吸器症状がでてきたら医療機関を受診し、お風呂で溺れたことを医師に伝えてください。
- 飲料水について
-
- Q飲み水(飲料水)の検査にはどんな種類があるの?
- A
飲料水の水質検査は健康に関する項目(重金属や有機溶剤、大腸菌など)と品質に関する項目(硬度や泡立ち、臭いなど)について検査します。また、法律に基づいた検査では根拠法令ごとに設定された検査項目について調べます。
水道法 主に水道事業者(市町村等の自治体や専用水道の管理者)が対象です。 建築物衛生法 一定規模のビルや商業施設等が対象です。 食品衛生法 食品衛生法における許可届出施設(飲食店や食品工場)が対象です。
- Q飲料水の検査項目ってどうやって選べばいいの?
- A
法律に基づいた検査は項目や頻度が決まっているので、定められた通りに検査することが一般的です。
例えば建築物衛生法に基づく検査であれば、28項目と16項目の検査を1年に1回ずつ実施します。
その他味や臭い、色など使用していて気になることがあれば、水の種類や相談内容に応じた項目を提案します。
- Q井戸水が飲めるか検査してほしい
- A
井戸水を飲料水として利用する場合の検査も実施しています。
特に最近は発がん性や内分泌かく乱作用などが指摘される「PFAS」と呼ばれる化合物が注目され、全国的に地下水からも検出されていることから規制が強化されています。
聞きなれない化学物質や重金属類による健康への影響など、井戸水を使う際に感じている不安があれば、お気軽にお問い合わせください。
- Q管理しているアパートに受水槽があるんだけど、水質検査してたかな…
- A
ぜひ一度ご確認ください。
法律上の検査義務がない建物(小規模アパート・テナント・会社事務所など)であっても、受水槽の清掃点検や水質検査を怠れば、入居者や従業員からの苦情や解約にとどまらず、最悪の場合健康被害が生じて責任問題に発展する事も想定されます。定期的な検査を実施し、トラブルを回避しましょう。
- Q最近ニュースになってるPFASとかPFOAってなに?
- A
“PFASとは「ペルおよびポリフルオロアルキル化合物」の略称で、数千種類あると言われる有機フッ素化合物の総称です。
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸)はPFASの中で特に代表的な物質で、どちらも熱や薬品に強く分解されにくい性質があります。2025年の法改正により、PFOSとPFOAは水道水の水質基準項目に設定されました。”
- QPFOSは規制されているのになんで今問題になっているの?
- A
PFOSなどは熱や微生物、薬品や紫外線などでほとんど分解されないため、自然環境や生体内で何十年も残る「永遠の化学物質」と呼ばれています。
健康への悪影響が疑われるようになった2000年代から規制され始めましたが、過去に製造・使用されたものが大気・地下水・河川などを通して広く拡散し、それを取り込んだ人や動物の中で蓄積していると言われています。
- Q今飲んでる水にPFOSとか入ってないか心配…
- A
ご安心ください。
普段私たちが飲む水道水(上水道)は定期的に検査が行われていて、PFOS・PFOAを含む基準項目をしっかり検査しています。
ただし、井戸水は検査されていないことが多いので、飲み水にするのであれば年に1回はチェックしておくと安心です。
また、PFOS・PFOAは活性炭タイプの浄水器を使うと除去できると言われているので、心配な方はチェックしてみてください。
- 食品検査について
-
- 賞味(消費)期限検査について
-
- Q消費期限と賞味期限はどう違うの?
- A
消費期限は安全性を、賞味期限は品質の保持を担保する用語です。
○期限を過ぎて食べたら具合が悪くなるかもしれない⇒消費期限
○期限を過ぎて食べたら美味しくないかもしれない””目安””⇒賞味期限
以前は期限が5日以下を消費期限、5日を超えると賞味期限と区別されることもありましたが、
現在は日数によって区分していません。
- Q期限が切れた食品は食べられないの?
- A
消費期限が切れた食品はその安全性を担保できないので、食べることは避けてください。
また、製造者が再利用(加熱して別の製品に作り直す等)することは不適切といえるでしょう。
一方賞味期限は、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではないので、
食品ロスの削減に取り組むうえで、賞味期限を再利用日とすることは十分に考えられます。
この時に、食品の特性を理解し、それに応じた検査を実施していることが重要です。
- Q期限設定のために検査はしないといけないの?
- A
期限の設定は科学的かつ合理的に行うことが必要です。
他社で見た目は同じような製品を取り扱っていても、原材料や製造方法、製造環境が違えば検査結果も変わります。
責任をもって期限表示するためには検査は必須といえるでしょう。
- Qすべての製品について検査しないといけないの?
- A
本来は製品ごとに検査を行うことが望ましいです。
しかしながら、製品を特性ごとに分類し、代表的なものを検査することも可能です。
どのように分類したらいいかわからない場合は、お気軽に相談ください。
- Q期限設定のためにはどんな検査をしたらいいの?
- A
適切な期限設定のためには、食品の特性に応じた検査項目を選ぶ必要があります。
例えば、冷蔵製品であれば「低温細菌」を、真空包装や脱酸素を行う製品であれば「嫌気性(芽胞)菌」を、それぞれ一般的な衛生指標として用いられる一般生菌数や大腸菌群と組み合わせると効果的です。
また、微生物検査以外にも、pHや水分活性、酸価、過酸化物価等の理化学検査も有効です。
- Q安全係数ってなに?
- A
安全係数は、製品の品質のばらつき等を考慮して、設定期限と検査日の間の日数を決めるときに使う数字です。
一般的には微生物が増殖しやすい食品(消費期限設定の弁当や惣菜)は安全係数を0に近づけ、品質が変わりにくい食品(レトルト食品等)は安全係数を1に近づけます。
例1)菓子の消費期限を3日にしたい→安全係数0.8→「3÷0.8=3.75」⇒4日後に検査
例2)冷凍食品の賞味期限を6か月にしたい→安全係数1→「6÷1=6」⇒6か月後に検査
- Q食品特性に応じた検査項目ってなに?
- A
食品特性に応じた検査項目とは、食品そのものの特性のほかにも、包装形態や保存温度等を総合的に考慮した危害要因に対応する項目を指します。
以下に例をまとめましたので、ご参照ください。●食品分類によるお勧めの検査項目
〇弁当(米飯類);セレウス菌、黄色ブドウ球菌
〇餅;真菌、セレウス菌
〇生洋菓子;サルモネラ属菌
〇惣菜類;腸管出血性大腸菌(O157)、腸炎ビブリオ(魚介類)、カンピロバクター(食肉)
〇ヨーグルト;酵母、大腸菌群●包装形態や保存温度によるお勧めの検査項目
〇保存温度が冷蔵の食品;低温細菌
〇レトルト食品等の真空包装食品;嫌気性芽胞菌
- ノロウィルスについて
-
- Qノロウイルスってなに?
- A
ノロウイルスは、人の腸管で増殖し、主に嘔吐・下痢・腹痛などを起こすウイルス性胃腸炎の原因ウイルスです。
ワクチンはなく、特異的な治療薬もないため、予防対策が非常に重要です。
- Qノロウイルスはどんな時期に流行しますか?
- A
ノロウイルスによる感染性胃腸炎・食品による食中毒は1年を通じて発生しますが、特に冬期(11〜翌年3月頃)が流行期です。
弊社では10-3月の定期検便検査を推奨しています。
- Qノロウイルスはどうやって感染しますか?
- A
主な感染経路には次のようなものがあります
・ウイルスに感染した調理従事者が食品を汚染して感染(食中毒)
・二枚貝(牡蠣など)を生食または十分加熱せずに喫食して感染(食中毒)
・ウイルスに感染した人の嘔吐物や糞便から感染(感染症)”
- Qノロウイルスの主な症状は?
- A
嘔吐・下痢・腹痛が主症状で、発熱することもあります。
免疫力の弱い子ども・高齢者では脱水や誤嚥などにより重症化することがあります。
- Qノロウイルスを予防するにはどうしたらいいですか?
- A
食事前やトイレの後、調理前などに手洗いを徹底しましょう。
また、二枚貝などの食品は85℃以上で90秒以上加熱してください。
食品製造施設においては、 下痢・おう吐等の症状がある人は調理業務に従事せず、普段から調理器具の洗浄・消毒などの衛生管理を適切に行うことが重要です。
- Qノロウイルス対策として、食品を取り扱う施設で特に注意することはありますか
- A
国のガイドライン(大量調理施設衛生管理マニュアル)では、適切な手洗いや加熱殺菌のほか、調理従事者の健康状態の確認と記録やノロウイルスの検便検査について記載されています。
各施設の衛生管理者は以下の事項をチェックしてみましょう。
・調理従事者の毎日の健康確認・記録をしているか。
・流行期(10-3月)にはノロウイルスの検便検査を実施しているか。
・ノロウイルス対策を含む衛生管理計画を策定しているか。
・発症(疑い)者発生時に迅速に対応するための手順が整備されているか。
・これらのマニュアルを従業員に説明・周知しているか。
- Q嘔吐物の処理はどのようにすればいいですか?
- A
ノロウイルス患者の嘔吐物中にはウイルスが大量に含まれ、直接取り扱うことは危険です。また嘔吐物中のウイルスを直接不活化することは非常に難しいと言われています。
ウイルスを周囲に広げないために、次の手順で処理しましょう。
①使い捨ての手袋やエプロンを身につける
②布やペーパータオルで嘔吐物を静かにまとめる
③嘔吐物のあった部分とその周囲を二酸化塩素系薬剤等で消毒して拭き上げる
④使用した器具類をビニール袋に密閉して廃棄する
- 検便について
-
- ノロウィルスについて
-
- Qノロウイルスってなに?
- A
ノロウイルスは、人の腸管で増殖し、主に嘔吐・下痢・腹痛などを起こすウイルス性胃腸炎の原因ウイルスです。
ワクチンはなく、特異的な治療薬もないため、予防対策が非常に重要です。
- Qノロウイルスはどんな時期に流行しますか?
- A
ノロウイルスによる感染性胃腸炎・食品による食中毒は1年を通じて発生しますが、特に冬期(11〜翌年3月頃)が流行期です。
弊社では10-3月の定期検便検査を推奨しています。
- Qノロウイルス対策として、食品を取り扱う施設で特に注意することはありますか
- A
国のガイドライン(大量調理施設衛生管理マニュアル)では、適切な手洗いや加熱殺菌のほか、調理従事者の健康状態の確認と記録やノロウイルスの検便検査について記載されています。
各施設の衛生管理者は以下の事項をチェックしてみましょう。
・調理従事者の毎日の健康確認・記録をしているか。
・流行期(10-3月)にはノロウイルスの検便検査を実施しているか。
・ノロウイルス対策を含む衛生管理計画を策定しているか。
・発症(疑い)者発生時に迅速に対応するための手順が整備されているか。
・これらのマニュアルを従業員に説明・周知しているか。
- Qノロウイルスの検便検査にはどんな意味がありますか?
- A
検査には食中毒を予防し、かつ社会的な信頼を得る効果があります。
1無症状保有者の把握
ノロウイルスに感染しているけれど無症状の人(不顕性感染者)を早期に発見することで、大規模集団感染のリスクを低減します。
2感染者への対応
下痢等の症状がなくなってからもウイルスは排出されます。過去に感染した調理従事者が安全に調理業務に戻ることを助けます。
3信頼性・リスク低減
「検査を実施している」ということを示すことは、利用者や取引先の信頼性向上につながります。
- 商品について
-
- サニトークシリーズについて
-
- Q安定化二酸化塩素とはどういうものですか?
- A
安定化二酸化塩素は元来不安定で刺激性のある二酸化塩素ガスを水溶液中に安定的に溶解させ化学薬品として容易に使用できるようにされたものです。塩素とは異なり強力な酸化作用で微生物を攻撃し、また悪臭物質を分解します。二酸化塩素はWHO(世界保険機構)でもその安全性を認め、A1ランクに認定されています。日本では小麦粉の殺菌剤として使用され、パルプの漂白、プール水の殺菌、飲料水の殺菌に認められています。
- Q安定化二酸化塩素による殺菌を教えてください。
- A
二酸化塩素は塩素と異なり、酸化作用により微生物を攻撃します。次亜塩素酸ソーダのようにトリハロメタンのような副生成物の産制がごく微量であり、ウィルスや芽胞菌にも効果があり現在まで耐性菌の出現は認められていません。二酸化塩素による殺菌は文献では滅菌に近いともいわれています。
- Q安定化二酸化塩素による殺菌や消臭の分野を教えてください。
- A
二酸化塩素による殺菌や消臭はさまざまな業種で使用されています。微生物制御が必要な場所、悪臭の発生する場所など用途は数多くありますのでお困りの分野についてお問い合せください。
- Qノロウイルスに有効な薬剤はどのようなものですか?
- A
ノロウイルスはアルコールに耐性があり、あまり効きません。
そこで手に付着したウイルスは手洗いによって取り除くことが重要です。
また、調理器具やトイレの消毒には次亜塩素酸ナトリウムや二酸化塩素系の薬剤が有効です。
弊社のサニトークシリーズは活性化二酸化塩素を主成分とする薬剤です。
トイレや嘔吐物を処理した後の壁・床の消毒および消臭に役立ちます。
- Q嘔吐物の処理に役立つものはありますか?
- A
嘔吐物の処理において重要なのは①汚染を広げないこと、②適切な薬剤を選ぶことです。
そのために嘔吐物処理剤の「クリーンぽいっ!」と除菌消臭剤「サニトークシリーズ」をおすすめします。
「クリーンぽいっ!」は嘔吐物の水分に吸着し、素早く嘔吐物を固めてくれます。
嘔吐物の処理が簡単になると同時に消臭効果もありますので、飲食店の客席等の迅速な対応が求められる場面でも活躍します。
「クリーンぽいっ!」で嘔吐物を除去したら、活性化二酸化塩素を主成分とする「サニトーク」を広く吹きかけ拭き上げてください。
- その他の商品について
-
- Q嘔吐物の処理に役立つものはありますか?
- A
嘔吐物の処理において重要なのは①汚染を広げないこと、②適切な薬剤を選ぶことです。
そのために嘔吐物処理剤の「クリーンぽいっ!」と除菌消臭剤「サニトークシリーズ」をおすすめします。
「クリーンぽいっ!」は嘔吐物の水分に吸着し、素早く嘔吐物を固めてくれます。
嘔吐物の処理が簡単になると同時に消臭効果もありますので、飲食店の客席等の迅速な対応が求められる場面でも活躍します。
「クリーンぽいっ!」で嘔吐物を除去したら、活性化二酸化塩素を主成分とする「サニトーク」を広く吹きかけ拭き上げてください。